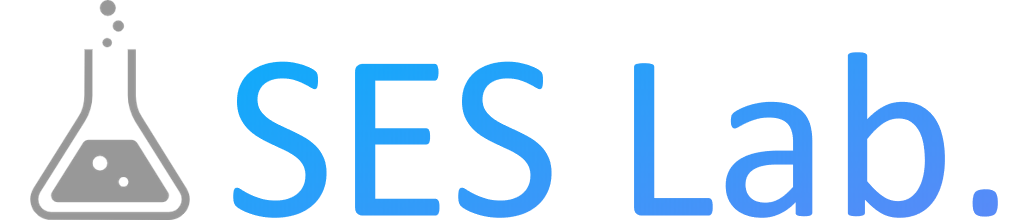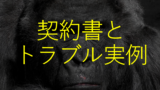SESの契約についての記事を記載したところ、エビデンスメールについての質問をいくつかもらいました。
備忘録としてこちらに記載します。
そもそもエビデンスとは何か

エビデンスの意味を英語から理解しよう
エビデンスは英語でevidenceと書きます。
日本語での意味は証拠・根拠、証言、形跡ですね。
ビジネスにおけるエビデンスも基本的に同じ意味です。とくに証拠という意味で覚えて問題ないでしょう。
エビデンスという言葉の使い方
エビデンスという言葉は以下のように使います。

クライアントの条件が変わる可能性があるので、今回の会話内容をエビデンスとして議事録に残しておきましょう

トラブルになったけど、エビデンスがメールに残っていたおかげでトラブルの解決ができました

カスタマーの入場意思をエビデンスとして回収してください。
概ねエビデンスを「証拠」と読み替えても内容は理解できると思います。
ビジネスにおけるエビデンスは何が該当する?

すべての情報がエビデンスになりえる
口頭、電話な度、文字になっていない情報でもエビデンスになりえます。
ただし、「なりえる」と言っているだけで、エビデンスに必ずしもならないことが実情です。
口頭、電話等の文字情報としてのこっていない情報については、トラブル発生した際にエビデンスとしての効力を持たない可能性があるのです。
基本はエビデンスメール。客観的に内容が証明できるものだけがエビデンスの効力を持つ
では、ビジネスの現場ではどのようなものがエビデンスとしての効力をもつのでしょうか?
- 第三者が見ても、客観的に一意になる情報
- 変更をすることができない情報
- 双方が合意している情報
基本的には上記を満たしている場合に、エビデンスとして扱うことができます。
「第三者が見ても、客観的に一意になる」とは、誰が見ても同じ理解をできる情報ということです。文面に残す際は、関係者だけの間で通じる指示語等はさけ、明確に記録をするようにしましょう。
「変更をすることができない」とは、チャットなどのように後から変更できないということです。チャットにたいして、メールであれば、双方が変更できない情報を渡すことができます。
「双方が合意している」とは、お互いが了承しているという意味です。他社の人が議事録メールを送ってきて、自分にとって不利な情報を記載されてしまったり、勘違いによって話が進んでしまうこともあるので、注意が必要です。
ビジネスにおけるエビデンス6つのルール

ルール1:エビデンスはとにかくメールにする
最初のうちは何がエビデンスとして扱えるかわからないと思います。
なので記録をする場合はとにかくメールで記録をしましょう。
ルール2:すべての内容をメールに残す
トラブルが発生した際は、何がエビデンスになるのかわかりません。
なのでとにかく関わっている案件に関して、何か進捗が合った場合は議事録メールに記録を残しましょう。
最初のうちは、進捗がなくても記録を残すくらいで充分です。
ルール3:1つの案件についてのメールは同じ件名(スレッド)で行う
後で検索しやすいように、1つの案件に対してのエビデンスメールは1つの件名(スレッド)で行いましょう。
ルール4:合意していることをメール文面に明記する
エビデンスメールでは、合意したことが重要になります。
なので「本目メールの内容で承りました」や、「本メールの内容に齟齬や指摘がある場合はOO月OO日OO時までにご連絡ください。ご連絡ない場合は本メールの内容で合意したものとします」という文面を記載しましょう。
ルール5:関係者全員に送信する
エビデンスは関係者の見えるところで共有しましょう。
議事録であれば、参加者に対してTo配信をし、関係者にはCc配信をします。
ルール6:引用するときは時間と件名を伝える
何かトラブルがあった時や、過去の話をする際は、曖昧な情報を元にせず、エビデンスメールの情報を元に会話しましょう。
「oo月oo日oo時のメールでこのように言っていますよ」などのように、お互いが情報を正しく認識した上で会話できるように目線をあわせましょう。
まとめ
- エビデンスはメールで残そう
- エビデンスメールの効力は?
- エビデンスメールの6つのルール
エビデンスメールはビジネスにおいてトラブルの際の助けになるだけではなく、円滑にビジネスをすすめる上でも重要になってきます。
円滑なビジネスを行うためにも、エビデンスの扱いをしっかりと行いましょう。