SES営業では面談がつきものです。
実際にスキルのあるエンジニアであっても、面談がヘタで入場につながらないことがあります。
エンジニアさんも、優秀であっても落ちてしまうことがあるので、本人も辛いと思います。そんな状態にならないように、事前に面談について確認して行きましょう。
SESの面談とはそもそもなに?

面接と面談の違い
本来、面接と面談はその目的が違います。
【面接】 選考の一環。相手のスキルなどを確認するためにおこなう。
【面談】 その人の人間性や、本人意思を確認する場所。本来は選考とは関係ない
SESや客先常駐の場合は、面談といいっていますが実態として面接をしています。
結局選考のための面談になっているので、「面談」という呼び方をしていても、実態は「面接+面談」の内容になっているわけですね。
とにかく、SESや客先常駐において、「面談」と言われたら「面接も含んでいるんだな」と理解してください。
SES面談は違法なの?
SESにおいて、皆が「面接」ではなく「面談」といっているのには理由があります。
厳密に考えると、SESにおいてエンジニアにたいして面接はしてはいけないんです。この部分は法的に未整備であり、違法とは言えない状態にあります。
理由として、SESでは、相手フリーランスと契約するのではなく、SES会社と契約します。そして、納品物は指示しますが、具体的な作業内容は指示しない(指揮命令権がない)ので、誰が作業をするかは本来関係ないはずなのです。
最近はSESやフリーランス周辺の環境も変わってきたので、法整備もこれから追いつくことになるでしょう。
面談に向けての事前準備

面談とは言え、選考の意味も含んでいるので、事前に準備が必要です。
SESの面談に来る人は、意外とこの準備をしたことがない人が多くいます。
選考を含んでいることを本人に伝え、しっかりと準備をしましょう。
案件情報をまずは確認
面談に落ちないための原則は「相手の求めている答えを回答する」です。
まずは、求人情報から相手の求めている人物像を推測しましょう。
特に確認すべきは以下です
- 運用なのか、開発なのか
- 長期案件なのか、短期案件なのか
- 開発環境に対しての経験はどこまであるのか
- 他の人との連携が必要なのか、作業重視なのか
上記にを確認して、それぞれどのような回答があるのかを考えましょう。
このとき、確認するのは、回答内容だけではなく、身振りや振る舞いまでをチェックする様にしてください。
エンジニア自身でこれらをチェックすることができるのがベストですが、自身でできな場合は営業担当や人事に協力をしてもらってでもチェックを完遂します。
SES会社には人事がいることが一般的なので、人事と一緒に、面談の回答方針があっているかの確認をしてください。
フリーランスのエンジニアのかたは、SES会社を使うメリットがこの面談対策にあるということを忘れないでください。
プログラマのスキルシートを再確認・調整
プログラマのスキルシートを企業の求める姿に調整します。
企業の求めているスキルで、関わったことがある内容についてはより厚めに書いてください。開発環境の内容も、記載忘れがあれば書き足す様にしましょう。
面談時に質問されることをスキルシートから推測
ここまでで、案件内容と、自身のスキルシートの振り返りをしてきました。
案件内容とスキルシートを照らし合わせて行きます。
案件内容から推測できる、求めているスキルを一度リストにします。このリストにたいして、スキルシートに記載されている内容が、充足するものになっているかを確認してください。
この「充足」というのは、エンジニア自身では判断し辛いと思います。
そこでSES営業に協力してもらって、「充足」の判断をしていきましょう。
「充足」していない内容に関しては、満額回答できなくても「OOOの経験はありませんが、OOOの経験があるのでカバーできます」などの様に、保険プランを用意してください。
面談当日。質問に回答する

相手の求めている人物になりきろう
事前準備で考えた、どんな人を求めているのか。この人物だったらどういう回答、振る舞いをするのか考えてみましょう。
この人物からできるだけ離れないように行動します。
例えば、長期運用案件の面談であれば、変化をもとめず、ルール化したことを確実にこなすことのできる人物になりきます。
ここでは、嘘をつくということではなく、本当は新規開発がやりたいという思いがあっても、そのことは話さないということです。
嘘はダメです。余計なことは言わないと考えましょう。
聞かれたことに対して、結論から話そう。
何か質問されたら、YES,NOや、短答で一度答えましょう。
そのあとに説明として詳細をお話していきます。
理由や状況説明から話してしまうと、聞き手に言いたいことが伝わりません。
また、会話の通じない人だというレッテルをはられてしまい、オファーをもらうことがむずかしくなります。
結論から話すことによって、自身も話をうまく組み立てることができます。
結論→説明(理由や状況)→結論 の順に話すとうまくいきます。
できないことを聞かれたらどうする?
できないことを聞かれた場合は、単純にできないとは言いません。関連業務の説明をして、最終回答としては「OOOの経験があるのでOOOもできると思います」の様に、可能性の話しをしましょう。
SES面談のよくある質問と回答例

先程の質問回答の原則を元に、実際の面接でよくある質問と回答例をみていきます。
運用案件の場合

これからのキャリアプランでやりたいことや伸ばしていきたいスキルはありますか?

あります。
自分の長所はできることを確実にこなすことだと思っています。この長所を伸ばすために、オペレーターや保守の案件に関わって行きたいなと思っています。
本当は新規開発の案件がやりたいなと思っていても、上記のような回答をすることがあります。
この理由は相手に「求めている人物ではないな」と思わせないためです。
ただし、嘘はダメです。なので、自分の長所を伸ばすために「は」運用をやりたいという主旨で語ります。
自走力を見る質問の場合

これまでの仕事の中で、一番の困難を教えてください

一番の困難は、ゲーム事業における新規開発です。
まず稼働時間が多かったというのと、仕様変更が多く実装がなかなか進みませんでした。
その中で私は仕様変更がある前提で開発をしました。仕様変更があるとして、どのような変更になるかも含めてお話を伺いました。その変更に耐えることのできる開発を心がけていました。
この経験で、冗長性の高い開発ができる様になったと思います。
こういった質問の場合は、負の状態にたいして、自身で何ができるのかを自分で考えて行動できるかどうかを問われていることが多いです。
案件で求められているスキルに則して回答できるとなお良いと言えます。
稼働耐性を見る質問の場合

残業は大丈夫でしょうか?

大丈夫です。
家まで1時間程度かかるので終電は23時くらいになります。
残業の質問は、緊急時に対応できるかの質問です。
実際に残業がない会社であっても、残業可能かを聞いてくる会社は多くあります。
会社にとって重要なのは、残業をしてほしいということではなく、必要なときに残業をしてもらうことです。残業を最終手段として持っている人はそれだけでプラスに映ります。
ここで注意なのですが、残業時間について確認したい場合であっても、残業時間についての質問はしないでください。
残業できない人だと思われて評価が下がることがあります。
残業について確認したいときは、担当の営業さんに確認してもらいます。営業はこの質問をするときに、面談したエンジニアからの質問であることは伝えないので安心してください。
成長性を確認する質問の場合

これから習得したいスキルはありますか?

サーバーサイドのスキルを習得しようとおもっています。
現在はフロントエンドエンジニアとして業務をしていますが、このスキルをより高めるために、サーバーサイドの知識が必要だと考えています。
ただ、今後もやっていきたいことの中心はフロントエンドなので、あくまで補助的なスキルとして捉えています。
この質問は、成長性を確認すると同時に、その人のやりたいことや、努力ができる人間なのかを聞いています。
このときに、将来やりたいことを語ることになると思いますが、案件で求められているスキルに則した回答をすることです。
それでも受からないときにできること

正直いうと、面談は9割程度が準備力で決まります。
この準備は一人でできる人はほとんどいません。
フリーランスのエンジニアであれば、誰にも相談できないと思いますが、SESの営業等を通している場合は、営業に相談できます。
営業に相談すると言うことは、フリーランス就業のプロに相談するという意味です。
せっかくプロのサポートがついているのに使わない手はありません。
また、SES営業がエンジニアにたいして価値発揮する部分はそこしかありません。仕事なので当然やります。逆にやらない営業がいたら、その営業は仕事をしていないことになります。遠慮せずに協力してもらいましょう。
エンジニアは営業をうまく使って、本当にやりたい仕事を獲得していきましょう。
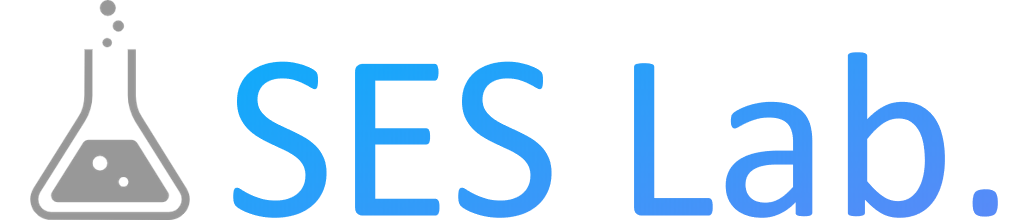


コメント
フリーのエンジニアです。
SESでのオファー頂いていたのですが、直前になってオファーがなかったことになりました。
こういったことはSESではよくあるのでしょうか
また、この場合の損害を請求することはできるのでしょうか
コメントありがとうございます!
頻繁ではないですが、SESではよく聞く話です。
自社では発生しないけど、四半期に2,3件は聞く程度の印象ですね。
もちろん付き合っているパートナーや、クライアント企業によってその発生頻度は異なると思います。
賠償請求についてですが、”オファー”の形式次第です。
オファーがメールのような形に残るものであれば賠償請求はできると思います。
口頭であり、オファーをもらったことが証明できないと厳しいかもしれません。
また、オファーが証明できたとしても、実際に賠償請求をするかどうかというのはまた別の視点が必要だと思います。
関係値を崩したくないクライアントであれば、賠償請求はしませんが、今後付き合いを持つ必要がなければ賠償請求をすることもあります。
(賠償請求がSES業界で実際に行われているかどうかは、これもまた付き合っているパートナーや、クライアント企業によります。)
今回コメント頂いたフリーランスエンジニア様の場合ですと、1つのクライアントがいなくなったからといって、困ることはないかとおもいますので、
賠償請求しても良いかもしれません。
(相手が大手であり、かつオファーが形あるものでしたら応じてもらえると思います。おそらく金額については、半月分程度の金額で着地すると思います。
半月もあれば次の契約先が見つかる~みたいな話で着地するかと。)
取り急ぎの対応としては、賠償請求しても良いかを担当者に確認することをおすすめします。
その際は賠償請求ではなく、「合意していただいた契約についてのご相談」という伝え方のように、こちらが攻撃姿勢に入っているような見え方をしないように注意してください。