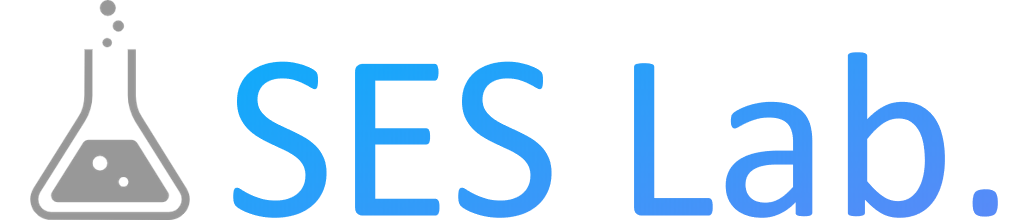先日、新卒の目標設定をおこないました。
目標設定をしたことで、新卒の働き方が明らかに変わっています。
今回は目標の設定の仕方について考えます。
主にマネージャーやチームリーダー向けに書いています。
主体性を持って目標と向き合う

まず、皆さんの会社ではどの様に目標設定をしていますか?
- 事業部長が長期目標から計算した数字を各営業に割当て、決定事項として通達する。
- 各営業が自身で決める。
- 営業単体の平均業績を元に各営業が決める。
いろいろな方法があると思います。
いろいろな方法はあるのですが、強い組織と弱い組織では大きく異なる点があるのです。
| 強い組織 | 弱い組織 | |
| Visionの理解 | 自分たちが目指す姿を明確に理解している。目指す姿を達成したときに、どんな状態になっているかを明確に想像できている。 | 自分たちが目指す姿を理解できていない。自分たちの目指す姿の達成のために、誰に何を提供しているのか理解できていない。 |
| 目標数字の根拠 | Visionを達成している状態から逆算している。目標は短期、中期、長期の視点で考え、単月、四半期、半期、年間の目標を設定している。また、その根拠を皆が語ることができる。 | 目標数字の根拠を全く理解していない。なぜその数字が必要なのかも理解できていない。 |
| 達成難易度 | 達成できるかできないかの絶妙なラインで目標を設定する。全力で仕事に向き合い、知恵と工夫があれば達成ができる数字目標として設定している。 | 前年と同程度の努力で達成できる目標、達成不可能な目標、自分ではどうしようもない外部要因によって達成可否が分かれる目標を設定している。 |
| 意思決定者 | 目標を追う人自身。周囲のサポートを受けた上で決定する。 | 事業部長など、自身の上長。目標を追う人自身は決定しない。 |
強い組織は目標の意義を自身が理解し、主体性を持って決めているということが大きく違います。
目標設定は、各営業の活動に影響を与えるとても重要な要素です。
強い組織の目標は、営業自身が自己成長のために努力することをサポートし、自身を会社にとって必要不可欠だと思わせます。
弱い組織の目標は、営業自身が会社に利用されていると思わせてしまいます。
マネージャーやチームリーダーは設定した目標が各営業の成果に大きく影響をあたえ、退職率にも影響を与えることがあるということを理解して下さい。
Visionの理解

強い組織では上からおりてきた数字をそのまま鵜呑みにして追うことはしません。
「なぜ目標は設定されるのか」に書いてあることは、経営目線で目標について書いてあります。
経営目線では上記の考え方でも良いのですが、組織として、営業単体として、その考え方をそのまま伝えてはいけません。
営業メンバーは押しつけられた目標として認識してしまうかもしれません。
「なぜ目標は設定されるのか」というのは観点として、会社人が当たり前に持っているべきものであり、その上でどう目標と向き合うのかを考えましょう。
強い組織のメンバーは主体性を持って目標を決定しています。
この「主体性」を持つためには、必要なステップがあり、目標設定をする上でのステップを正しく踏むことによってはじめて「主体性」が作られます。
- Visionを正しく理解する
- Visionが達成されたときの状態を明確にする
- Vision が達成されたときの状態になるには何が必要か理解する
- 理解した必要要素は、短期、中期、長期でそれぞれどのような状態になっているかを明確にする
- 短期、中期、長期を達成している状態にするための目標を数字に落とし込む
上記を一つひとつ、営業自身が理解して目標の設定をしていきます。
逆に言うと、理解出来ない場合は、次のステップに進んではいけません。
ステップの確認作業中に、疑問を感じた場合は、一つ前のステップに戻ります。
営業がこれらのステップを踏めない場合は、営業の活動は「売上を作るための押しつけ」になってしまいます。
「押し付け」をやっている営業は、当然仕事も楽しくなく、仕事に対して後ろ向きになってしまいます。そうなってしまった営業がトップセールスになることは絶対に有りえません。
また、上記のステップを営業単体が組織上長と合意を持って進めていくことが重要です。
必ず、会社に押し付けられた目標ではなく、自身の成長や、社会的意義のために数字を設定する様にしてください。
そうしないと、仕事で辛い経験をしたときに、目標から逃げてしまいます。
また、逃げることがクセになり、営業として、社会人としての成長がなくなってしまいます。
目標数字の根拠

先程のステップを踏むことで、目標数字の根拠を考えることができます。
- Visionを正しく理解する
- Visionが達成されたときの状態を明確にする
- Vision が達成されたときの状態になるには何が必要か理解する
- 理解した必要要素は、短期、中期、長期でそれぞれどのような状態になっているかを明確にする
- 短期、中期、長期を達成している状態にするための目標を数字に落とし込む
ここでの考え方は、
Vision>長期目標>中期目標>短期目標
の順に考えて行くと良いでしょう。
達成難易度

具体的数字になる難易度は「全力で取り組んだ状態」で、営業自身が「主体性をもって」決定することが重要です。
ステップでいうと太字の部分です。
- Visionを正しく理解する
- Visionが達成されたときの状態を明確にする
- Vision が達成されたときの状態になるには何が必要か理解する
- 理解した必要要素は、短期、中期、長期でそれぞれどのような状態になっているかを明確にする
- 短期、中期、長期を達成している状態にするための目標を数字に落とし込む
営業というよりも会社人として、社会人として目標を達成することは、人間的な喜びの一つです。
この喜びは将来的な誇りであったり、人間的能力として、転職してもどこまでも持ち込むことができます。
転職が当たり前になった時代において、会社から従業員に対してプレゼントできる数少ないモノの一つかもしれません。
この誇りや能力は、簡単に手の届く目標を達成しても得ることができません。
ありとあらゆる工夫や努力をすることを通じて獲得できるモノなのです。
また、簡単な目標を達成したとしても、
- 他の会社では通用しないのではないか
- 今の会社では期待されていないのではないか
という不安につながってしまうことも多くあります。
反対に、達成が難しそうな目標を設定した際には、
- 困難に向き合うことが楽しい
- 自身の成長が楽しい
といった考え方を獲得して成長すること自体が楽しいというポジティブな発想を持つことができる様になります。
意思決定者

目標は押し付けになってはいけません。
目標を追う人自身が主体性を持って考えることが重要だといいました。
自分自身のために仕事を行っているということをしっかりと認識できる目標を作りましょう。
そのためには、意思決定者は営業本人にしてください。
営業自身が低すぎる目標を提示してきた場合には、自身で目標設定のステップを再度踏んでもらい、その中に、自身が人間として、どこまで成長しないと行けないのかを考えてもらいましょう。
人間的成長をするために、目標数字を総設定するのかを考えてもらいましょう。