案件ガチャとは、実際に働いてみないと案件の中身がわからない案件のことを言います。
そんな案件ガチャの意味や、状況や対策について解説していきます。
案件ガチャとは
案件ガチャの意味
案件ガチャとは、「働く前にわかる業務状況」と、「働いた後でわかる業務実態」に乖離があること、またその状況を指します。
簡単にいうと、就業前と後で、情報格差がある状況のことです。
例えば、以下の状況が案件ガチャに該当します。
- 実際に働いてみないと案件の業務内がわからない
- 実際に働いてみると、紹介されていた業務内容とちがう
- 実際に働いてみると、業務内容の制限が多く、思ったようにスキル発揮できない
案件ガチャの使用例

あの営業から紹介される仕事は業務実態と案件情報が違っていて案件ガチャみたいなものだよな

あの営業は、しっかりと業務内容を確認してから紹介してくれるから案件ガチャになることが少ない

案件ガチャだと思って働いたけど、とても働きやすい環境だった

この案件は入場しないとどういう環境かわからない。案件ガチャだとは思うけど、単価が高いので入場してみようかな
上記のようにマイナイメージで使われることが多いようです。
案件ガチャが発生する状況

案件ガチャというのは情報量の格差によって発生します。
なので、案件ガチャというのは、情報量の格差が発生しやすい環境でよく起きます。
案件ガチャが発生しやすい状況
案件状況がよくわからない状態のときに発生します。
深い商流で案件を受けた時
商流が深いと、案件の情報が性確認伝わりにくくなります。
数人の営業が入ることで、案件情報がまるで伝言ゲームのように伝わっていき、最終的にエンジニアに渡る情報は正確ではなくなってしまいます。
セキュリティ意識の高い会社に入場した時
セキュリティ意識が高く、エンジニアの業務範囲に制限がかけられることがあります。
業務羽にに制限がかかると、案件情報のうち、開発環境としては準備されていても、実際の業務は行えないということが発生します。
セキュリティ意識が高い会社は、人材会社や金融系の会社が主な会社です。特に大手の場合はその傾向が強くなります。
また、大手の企業では、開発のごく一部しか担当することができない可能性もあります。その場合も案件ガチャになってしまうと言えるでしょう。
所属している会社都合で入場する案件が決まった時
SIerやSES企業において、会社都合で入場されられる案件は、案件ガチャであることが多いです。
エンジニアに案件に対してのマイナスイメージを持たせないためにも情報を詳しく伝えないことがあります。(実際には案件の詳細を理解していても、伝えない営業さんもいます。)
案件ガチャが発生しにくい状況
逆に情報格差が発生しづらい状況というものあります。
自社サービスを開発している会社に入場する時
担当するサービスが明確である場合は情報格差が発生しづらいです。なので案件ガチャには比較的なりづらいと言えます。
ただし、先述の通り、大手企業であったり、人材業界、金融業界などでは例外とも言えます。
あくまでベンチャー企業などの中小規模の自社サービス開発会社と思って頂いたほうが良いでしょう。
複数案件の中から、エンジニアにあう案件を選んだ時
複数案件あり、その中からエンジニアのスキルに見合った案件を選んだ場合は案件ガチャになりづらいです。
理由として、必要としているエンジニアのスキルと、案件で使用するスキルを考えてから入場できるからです。検討をしたり、案件元に交渉等をすることで、案件情報をより鮮明に見えてくることがあります。
高スキルを必要とする案件に入場する時
高いスキルを必要とする案件では、必要スキルが明確になっているので案件情報も明確になります。
特定のスキルが必要となるということは、その特定スキルがなにかを言語化する必要があります。言語化された情報から案件内容が理解できます。
案件ガチャに陥らないための対策
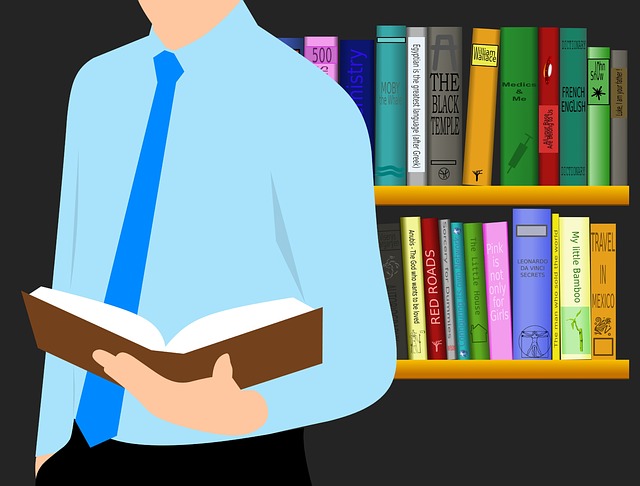
エンジニアにできること
他の人が持ってきた案件を受けるだけではなく、自分自身でも案件の情報に詳しくなりましょう。
具体的には・・・
- 案件を受けるときは、面談で案件詳細を直接聞く。
- 案件詳細を聞くときは、開発環境や開発分掌、開発範囲についても明確にする。特に「できないこと」について聞く。
- 案件を獲得するときは、必ず複数の案件から選ぶようにする。1人の営業や、紹介会社だけを信頼しきらない。
- 案件情報に対して詳しくなる。フリーランスの案件情報を常時モニタリングする。
- 入場を検討している案件については、知人に働いているっひとが居ないかを確認する。もし知人が働いている場合は、内情を確認する。
営業に任せず、自身でも情報を取りに行くことが大切です。
また、内情を知るには以下のようなサービスを使うことも有効です。
営業にできること
案件の情報を正確に伝えましょう。
案件のヒアリングに慣れてくると、開発環境についての質問もうまくなっていきます。
エンジニアの気になるポイントも理解できてくるので、ヒアリングシートをつくって、エンジニアの知りたい情報をもれなく吸収するようにしてください。
わからない部分については直接面談で聞けばよいのですが、案件について詳しく理解しているとエンジニアからの信頼が大きく変わります。
また、わからない部分については、わからないとはっきりと伝えてください。知ったかぶりをして誤った情報を伝えることだけはやめてください。エンジニアからも、クライアントからも信頼を失います。
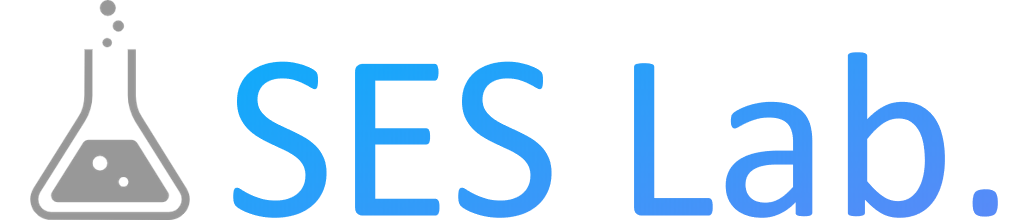

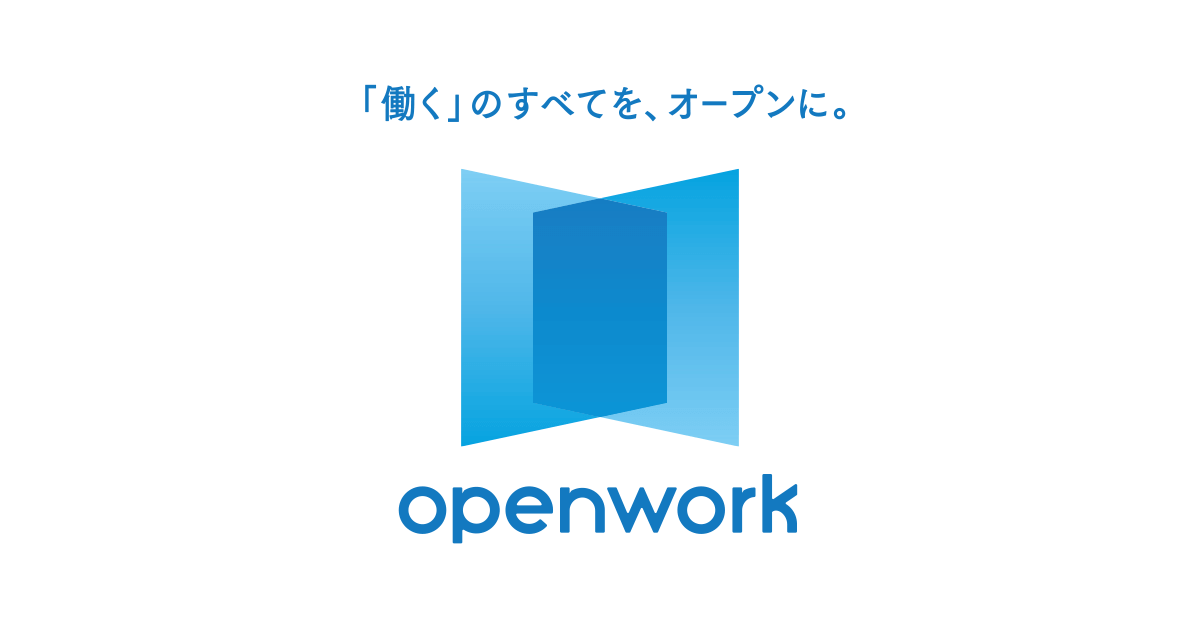
コメント
[…] SESは案件次第というお話でしょうか。案件ガチャという言葉もありますが、結局は案件次第。研修があるSES企業は駆け出しエンジニアや新たな言語を習得したいというエンジニアにとっては良いのかも。 […]